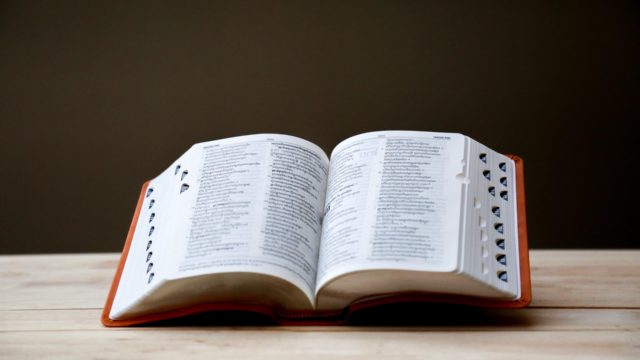新聞記事やニュースで見つけた、個人的に気になった会計関係の話題をご紹介します。
「非財務」情報に新たな商機
監査新常態(下)「非財務」情報に新たな商機
ESG巡りコンサル・保証、開示基準なく参入競争に
2021/1/15 日経新聞朝刊
上記の記事では、監査法人が従来求められてきた財務情報の監査のみならず「非財務」情報に関する監査も求められてきており、新たな収益源として重要な役割として認識されてきている、と言う内容が紹介されていました。
「財務」情報と「非財務」情報とは
記事の内容を詳しく紹介する前に、記事の中で出てきている単語の内容をご説明していきます。
- 財務情報:企業の財政状態を表す貸借対照表(B/S)、経営成績を表す損益計算書(P/L)、キャッシュフローの状況を示すキャッシュフロー計算書(C/F)等、企業の財務に関する情報
- 非財務情報:上記以外の情報。例えば、企業概要、ビジネスの状況、リスク情報、経営戦略、コーポレート・ガバナンス等、様々な種類がある。
- ESG:環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったもの。企業の長期的な成長のために必要であるという考え方が世界的に広まってきている
需要が増えてきている「非財務」情報を商機につなげる
監査法人が従来の監査で担保している「財務」情報だけでなく、近年投資家による評価の基準になっている「非財務」情報を新たな収益源にしつつあるそうです。
それがコロナ禍でより顕著になっており、財務指標だけでは見えてこない経営リスクをあぶり出し持続的な成長に向けたESGへの取り組みが企業価値を測る上で重要になっています。
EYジャパンが2020年7月に立ち上げた新組織である「LTV推進室」には、企業から非財務情報を企業価値向上のためにどのように投資家に説明するべきか相談が来ているようです。
LTVというのは「ロングターム・バリュー」の略で、利害関係者に対して長期的に価値提供できるように支援するコンサル事業を展開しています。
従来は企業の部長級からの相談が多かったが、経営層からの相談が増えてきたそうです。
コロナのような世界規模の災害が発生した場合に、どれだけ影響があるのかを投資家が判断するに当たり、非財務情報を適切に公開している企業が高評価されるのはある意味当然な気がします。
「非財務」情報の需要が高まっているため、この非財務情報の数値を高めるためのコンサル業務や、確かさを証明する保証が監査法人に新たな商機をもたらしています。
逆に投資家は公開されている情報がどこまで正確であり、その情報がどこまで網羅的に記載されているのかを見抜く能力が求められることになると思いますが、企業側に不利な情報を出さないというリスクについては監査法人が潰せるようにルールを整備することになるのだと思います。
非財務情報の開示が抱える課題
日経平均株価の構成銘柄で非財務情報を開示している企業のうち、外部機関から保証を受けている企業の比率が2019年に61%となり、5年間で2倍に増えているそうです。
企業がESGの取り組みをアピールしたい場合、事実上監査法人や審査機関の保証が必須になっています。
現在は上場企業でも積極的に動いている企業が中心ですが、今後はどんどん採用する企業が増えてくるはずです。
ただし、情報開示の基準が決まっている財務情報の指標とは異なり、非財務情報には開示の基準が定まっていません。
これにより企業間の比較ができず、投資家が判断するにあたりそれぞれの基準で比較をする必要があります。
非財務情報の保証における監査法人の優位性と展望
IFRS財団では現在乱立している開示基準を統合するための新組織を作る案が公表されたが、世界的な基準作りは始まったばかりでありかつ監査とは異なり保証は現状資格がいらないため他業種からの参入が相次いでいます。
そんな中、監査法人系の企業が保証業務のシェア6割程度を持っているようですが、国際標準化機構(ISO)の審査機関も4割ほどシェアを持っており、小規模な審査機関が破格の値段で受注を奪ってきているという、監査法人には逆風となっているそうです。
ただ、保証業務というのは、数値分析や書類確認などの間違いや不正を見抜く作業が監査と似ており、監査法人の方がノウハウはたまっており、その優位性をいかに企業側だけでなく評価する投資家側に認識してもらうかが重要みたいです。
監査法人では「非財務」情報保証の業務を積極的に推し進めていくようですが、それは主力である監査業務がこれ以上市場拡大の見込めないため業務であるためです。
監査以外でも経営コンサルやM&Aの支援も行っていますが、他業種との受託競争が激しく景気の波によって需要変動が大きい中で、それほど景気の影響を受けない(むしろ景気の悪い方が需要が上がる)「非財務」情報の保証において、どれだけ顧客をつかめるかが今後の成長に直結すると考えられます。